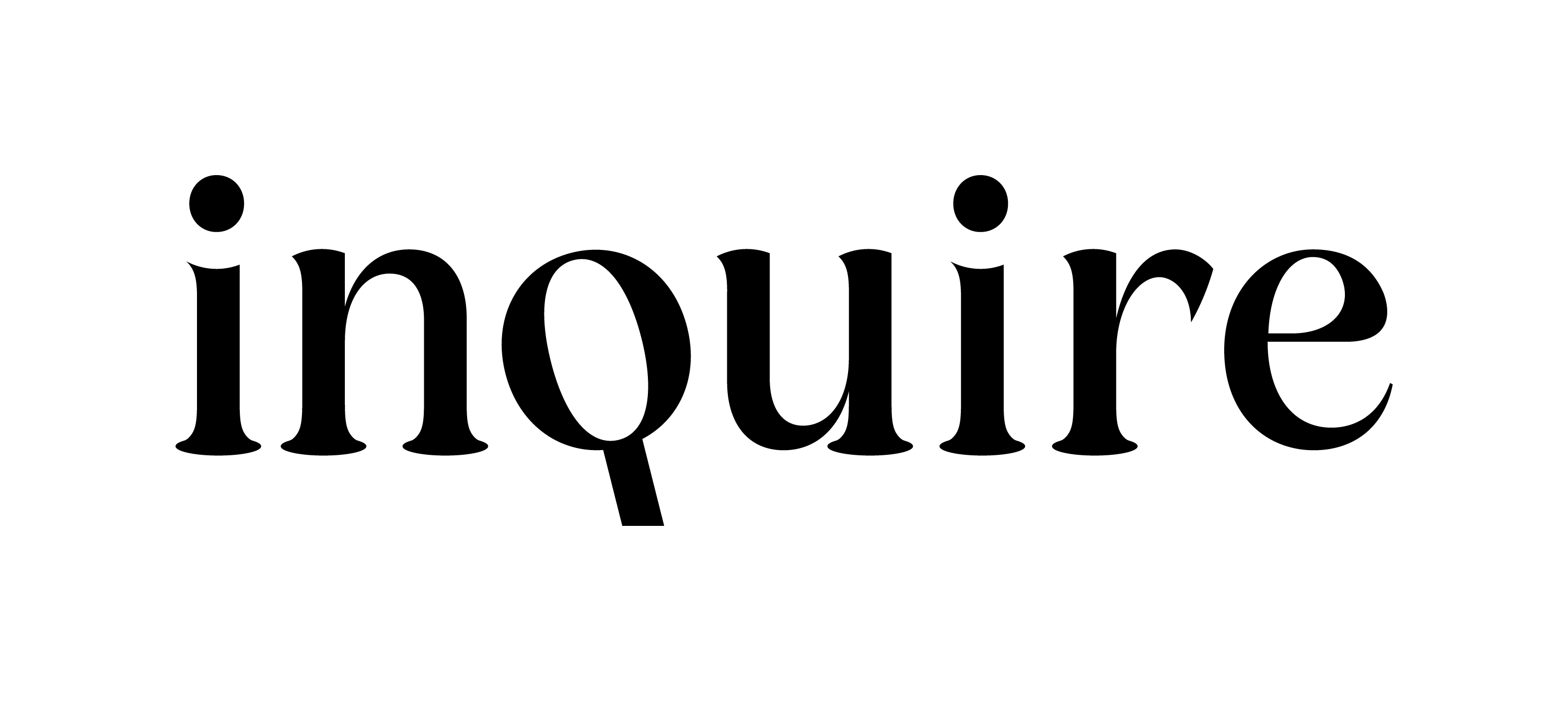⏩ 関税はメキシコ政府の薬物カルテル取り締まりがカギ?
⏩ 日本に追加の防衛増税も?アジア・ファースト主義者による圧力
⏩ ビッグテックの政治力が社会調査を困難に
⏩ トランプでも変わらないトレンドとは?
2025年1月20日(現地時間)、アメリカのドナルド・トランプが正式に第47代大統領に就任した。
ロイターの調査によれば、日本企業の約4分の3がトランプ大統領が自社事業にネガティブな影響を及ぼすと考えている。背景には、関税強化や米中間の貿易摩擦が懸念材料にある。
それらを含め、トランプ2.0は日本にどのようなリスクをもたらすのだろうか。

トランプ2.0がもたらすリスク
トランプ2.0がもたらすリスクは、大きく7つの視点から理解することができる。具体的には
- 関税
- 市場
- 移民労働者
- 安全保障
- テクノロジー
- DEI
- エネルギー・環境
だ。
1. 関税
1つ目のポイントとして、関税があげられる。日本貿易振興機構(JETRO)の調査によれば、在米日系企業のうち、各政策の中でも関税政策に影響を受けると答えた企業が最多で、72.4% はマイナスの影響を受けると回答している。
アメリカの通商法などに基づき、経済安全保障上必要な場合、大統領は例外的に議会の承認なしに関税を課すことができる。
トランプ大統領は、中国に対して 60% の関税をかけるとした他、アメリカに輸入される全ての商品に対して、普遍的に 10-20% の関税をかける構えを見せている。このユニバーサル・ベースライン関税と呼ばれるアイデアによって、アメリカの製造業を活性化させ、財政赤字の拡大を和らげるのに十分な税収が得られるという。
関税引き上げによる影響は、製品の生産地が日本にあるかアメリカにあるかで大きく異なるだろう。
この点を考慮すれば、たとえば、日本の自動車メーカーでも、関税政策から受ける影響は異なる可能性が高い。マツダやスバルのように、アメリカで販売する自動車の半分以上を日本から輸出している企業と、トヨタやホンダのように、その割合が少なく現地で生産体制を築いている企業とでは前者の方が関税の影響を受けやすい。
対メキシコ関税に注目すべき理由
そして、東京大学の鈴木一人教授が指摘する通り、関税政策については日米関係のみならず、対メキシコ関税にも注目する必要がある。中国への強硬な関税政策は予想通りの展開であり既定路線だったが、メキシコやカナダへの関税は新たな動きだ。
1990年代の旧北米自由貿易協定(NAFTA)成立以来、アメリカとメキシコ間の関税はほぼゼロだった(*1)。日本の自動車メーカーや電機メーカーは特に、メキシコの安い労働力コストを利用して、サプライチェーンを築き上げてきた。
トランプ大統領は2月1日、カナダとメキシコからの輸入品に 25% の関税を賦課する大統領令に署名した(発効は4日から)。同大統領は以前から、不法移民と麻薬(フェンタニル)の流入が無くなるまで、メキシコ(とカナダ)からの製品に対して 25% の関税を課す意向を示していた。
アメリカ商務省によれば、メキシコで生産された自動車の約 90% が輸出され、うち約 75% がアメリカ向けだ。そのうえで、北米で生産される自動車は、パーツの製造から組み立てなどの工程を経て、完成までに平均して8回ほど国境を超えると言われている。
また、日産などはすでに北米市場で苦戦を強いられ、人員削減に追われている。競争力の高いラインナップや価格で勝負することが苦しいメーカーにとって、対メキシコ関税の引き上げが新たな頭痛の種になることは間違いない。すでに2月3日の取引で、自動車メーカー各社の株価は軒並み下落した。

(*1)トランプ大統領は1期目の2020年7月、NAFTAの再交渉に乗り出し、サプライチェーンをより北米に集中させる目的で米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)を発効させた。
移転価格税制
こうした関税の引き上げ政策と北米という巨大市場を考慮した時、企業としてはジレンマに陥る。すなわち、巨大市場で取引をする合理性はあるが、高い関税は障壁になるということだ。
その場合、国内から海外子会社への販売価格を下げることで輸入価格を低く申告するという戦略がありうる。関税は輸入価格にかけられるため、価格を低く抑えれば、関税引き上げの影響を抑制できるという考え方だ。
ただ、そこには別の障壁として、移転価格税制の存在が指摘できる。日本も含め、各国政府は国内企業が海外子会社と取引する際の価格をウォッチしている。政府としては、国内企業があまりに安く海外の子会社へ製品を販売し、利益(とそれに伴う税金)を海外に移転していると判断すれば、申告漏れとして追徴課税する場合がある。
仮に、前述した対メキシコ関税などを受けてサプライチェーンを見直し、取引ルートを変更するなどした場合、企業は移転価格に関するポリシーも見直す必要があり、それらは新たな管理コストとなってのしかかる。
このように、関税の引き上げと言っても、どこの国に対してどの程度引き上げるか、現在や今後の生産体制といった企業ごとの事情によって、政策の影響はまちまちだ。
トランプ大統領が関税の引き上げに踏み切ることはほぼ既定路線となっているが、同大統領が関税にコミットし続けられるかについては疑問の余地もある。
関税の継続、注目すべき2つの動き
トランプ大統領による関税政策の継続性については、今後大きく2つの動きに注目が集まるだろう。具体的には、(1)メキシコ政府の麻薬対応(2)関税政策の矛盾だ。
(1)メキシコ政府の麻薬対応
第1に、メキシコ政府の麻薬対応があげられる。
トランプ大統領自身、関税に対する思い入れは強いものの、それを外交カードとして利用している側面もある。
たとえば、同大統領がデンマーク自治領のグリーンランドを購入するという方針を出した際、デンマーク側へ圧力をかけるため、関税の引き上げを表明した。これには、肥満症治療薬や糖尿病治療薬などを手がけるデンマークの製薬大手・Novo Nordisk(ノボ・ノルディスク)がデンマーク政府と交渉の場を設けるなど、事態の行く末を注視する姿勢が確認されている。

したがって、前述した対メキシコ関税の行く末は、同国政府の麻薬対応にかかっているとも言える。メキシコ治安部隊は2024年12月、1トン以上のフェンタニルを押収した。これは同国政府がおこなった過去最大の押収であり、その量は2,000万回分に匹敵する。
ただ、強い圧力を受けつつも、メキシコの麻薬カルテルは活発なビジネスを展開している。麻薬密売が「主要な経済」とすら言われるメキシコで、政府からの圧力が麻薬産業を崩壊させることは難しいだろう。
さらに、メキシコ政府は2月1日、アメリカに対して報復関税を発動する意向を示した。発動されれば、現地で生産活動をおこなう企業にとってはさらなるコスト増の可能性がある。
(2)関税政策の矛盾
2つ目は、関税政策の矛盾だ。前述したように、トランプ大統領が関税を発動する目的として、税収増、製造業の復活が意図されている。
たしかに、関税は在米業車が輸入品に対して支払う税金であるため、アメリカ政府にいくらかの税収をもたらす。そして、大統領が望んでいることは、関税によってアメリカの製造業を復活させることだ。たとえば、外国車を高価にすることで、アメリカ人が購入する外国車を減らし、彼らに国産車の購入を促す狙いがある。
しかし、ここで税収増と国内製造業の復活という目標が衝突する。すなわち、関税によってアメリカ人が外国車の購入を控えれば、そのぶん輸入が減少し、結果的に政府の税収は減少すると予想される。
そうした関税がもたらす帰結の矛盾が想定される中で、トランプ大統領がどこまで関税強化を進めるかは議論の余地がある。この議論の詳細は後述する。
いずれにせよ、関税引き上げに伴うコストは誰かが受け入れるしかない。メーカーが受け入れる場合は利益率の低下、消費者が受け入れる場合は価格の上昇という形で関税の影響が表出するだろう。
2. 市場
2つ目のポイントは、市場だ。トランプ大統領の就任によって、減税や規制の緩和などビジネスに親和的な環境が整う期待感が市場では強い。21日のアメリカ株式市場では、ダウ平均が1.2%、S&P500が0.9%、ナスダックが0.6%それぞれ上昇した。
とはいえ、そうした減税と同大統領の目玉政策である関税は、アメリカを再びインフレへと向かわせる可能性がある(*2)。前述した通り、トランプ大統領は就任式で、関税の具体策について言及せず、対中強行姿勢も影をひそめたため、投資家の間では安堵感が広がった。
ただ、2月にメキシコとカナダに対する関税を課す見込みであることが伝わると、株価は揃って下落した。日経平均株価は、トランプ氏の関税発言が伝わると、一時200円ほど下落した。関税をめぐるトランプによるシグナルに反応して、足元の状況はしばらく流動的になるだろう。
為替市場は、日米の金利差が縮小すると予測され、ドル売り・円買いの圧力が高まって円高・ドル安の傾向にシフトする可能性がある。
日銀は1月24日、トランプ大統領就任後の市場で大きな混乱がなかったことを受けて、政策金利を現行の 0.25% から 0.5% へ引き上げると発表した。日銀としては、今後も人手不足に伴う高水準の賃上げと物価上昇の継続が見られれば、さらなる利上げサイクルに入る公算が大きい。
一方の FRB(連邦準備制度理事会)は、今年少なくとも、あと1回の政策金利引き下げをするという見方が市場では優勢だ。
ただ、政策に左右された結果、円安・ドル高の傾向が変わらない可能性も残されている。減税や関税強化によるインフレを懸念した FRB が金利引き下げを停止すれば、そのぶん日米の金利差が縮まらず、ドル売りの圧力は弱まるという見方だ。その場合、1ドル=160円を超える水準にまで円安が進む可能性も否定できない。
(*2)ただし、関税が消費者物価指数(CPI)の計算に入らない商品を対象とする可能性もあるため、関税がインフレ材料になるという見方はやや単純化されている。
トランプの関税に対する”本気度”
以上を踏まえると、今後のポイントの1つは、トランプ大統領による関税強化への “本気度” だろう。
市場関係者が「トランプは関税を交渉材料として使っているに過ぎない」という見方を強めていけば、市場における関税強化への懸念は徐々に薄まる。すでに触れてきたように、トランプ大統領は関税を外交カードとして使う側面も見受けられるからだ。逆に、同大統領が「まだ準備していない」と語るユニバーサル・ベースライン関税の思惑が浮上すれば、市場は実際の政策として関税強化を織り込むだろう。
過去のトランプ大統領の言動を考慮すれば、関税強化が脅しに過ぎないと信ずるに足る理由はある。第1次トランプ政権は、メキシコに対して20-30%ほどの関税を課すと繰り返し脅したが、結局実現しなかった。このときは、メキシコがアメリカ、カナダを含めた貿易協定を見直すことで関税強化を避けた格好だ。
市場の見方は分かれており、現時点で決定的な判断材料は出揃っていないものの、中国を除けば、関税強化が外交カードとして利用される可能性は十分にある。
3. 移民労働者
3つ目のポイントは、生産力を支える移民労働者だ。全体として、トランプ政権が移民に対して強硬な姿勢を取ることは間違いない。
特に、前述してきた現地に製造工場を持つ日系企業は、移民減少の影響を受けやすいだろう。インフレや人手不足に頭を悩ませてきた企業にとって、移民の減少は、現地アメリカ人労働者の賃金上昇圧力となるため、さらなるリスクとなる。
ただ、トランプ大統領は移民に対して強硬な姿勢を貫いているものの、あらゆる移民を排除すると主張しているわけではない。同大統領は2024年6月、政権入りも果たしているテック業界の著名投資家たちとの会話の中で、高度教育を受けた移民であれば、グリーンカード(永住権カード)を受け取るべきで、それが可能となるよう約束すると発言した。
とはいえ、これらの移民労働者に魅力を感じる企業は、熟練労働者を欲しがるテクノロジーや医療業界などの大手企業に限られるだろう。したがって、高度な教育を受けた移民が、日系企業の経営状況に即座に大きな影響を及ぼすとは考えにくい。
いずれにせよ、数年ごと、あるいは大統領の外交戦略など不確定要素の大きい条件によって、労働力の確保は影響を受けやすい。その点を考慮すれば、Teslaやトヨタなどが進めるギガキャスト(細かいパーツを組み合わせるのではなく、一体型の部品を成型することで工程数や在庫管理コストを低減させる次世代型鋳造技術)のように、生産体制における抜本的な改革が求められるかもしれない。
4. 安全保障
4つ目のポイントは、安全保障だ。日本への影響を理解するためには、新政権のスタンスや人事をおさえる必要がある。
前提として、アメリカ政府当局者、委員会、シンクタンクなどは、同国が中国との戦闘を余儀なくされた場合、敗北する可能性があると警鐘を鳴らしてきた。
その意味で、安全保障をめぐるトランプ新政権の人事に中国への意識が強く出たことは自然な成り行きだった。たとえば、国務長官に任命されたマルコ・ルビオは対中強硬派として知られる。ルビオは2014年、当時の安倍晋三首相を訪問した際、同首相の防衛力強化に向けた取り組みを称賛し、中国の領土政策を非難した。
さらにトランプ政権は、エルブリッジ・コルビーを国防総省の政策担当次官に選んだと発表している。コルビー次官は、アメリカの最善の利益を考慮して、文字通りの孤立に向かうべきではないとしつつ、同盟国の負担の大半をアメリカが負い続けることも現実的ではないと見ている。

そのうえで、現在のアメリカにとって最大の脅威は(ロシアではなく)中国であるため、ウクライナに向けている支援を台湾にシフトさせるべきだと主張する。こうした一派は、アジア・ファースト主義者あるいはプライオリタイザー派と呼ばれ、アメリカの外交戦略において存在感を増している。
防衛増税強化か関税か
その中で、トランプ大統領は日米安保について目立った発言をしているわけではない。
ただ前述した点を踏まえると、トランプ政権は石破茂首相が語る日米同盟の対等化を逆手に取る形で、日本に対してさらなる防衛力の強化を求める可能性が高い。コルビー次官は2024年9月、日本経済新聞の取材に対して、防衛費を2027年にGDP比 2% に増やすという今の政府目標は不十分であり、速やかに 3% にしなければならないと語った。

トランプ政権発足後の1月21日、岩屋外務大臣とルビオ国務長官が会談し、日本は防衛力強化を引き続き推進していく姿勢を伝え、アメリカも抑止力強化の推進を継続するなど、両国の目線を揃えたという。

日本政府は防衛費を確保するため、2026年から法人税とたばこ税、2027年から所得税を引き上げる計画を取りまとめている。ただ、公明党内の否定派や国民民主党の反発にあえば、計画通りに進まない可能性もある。その意味で、自民党が国内の政治においてどれだけの主導権を握れるかは、今後重大な論点になる。
日本が防衛費の拡充に足踏みすれば、トランプ政権は日本に圧力をかけると考えられる。ここで言う圧力には、アメリカ軍駐留費の増額の要求、前述してきた外交カードとしての関税強化という交渉方法も含まれる。
したがって、安全保障という文脈において日本は、防衛費拡充のための増税をさらに進めるか関税強化を受け入れるか、という板挟みに直面するリスクに見舞われる可能性がある。現状、石破首相が安倍晋三ほどトランプ大統領からの信頼を獲得できるとは信じられていないし、報復関税に乗り出すシナリオも考えにくい。
5. テクノロジー
5つ目のポイントは、テクノロジーだ。トランプ政権のもとで、テック業界には大きく3つの変化が到来すると考えられる。
AI の規制緩和
第1に、AI の規制緩和があげられる。トランプ大統領はすでに、バイデン前大統領が取り組んだ AI 規制を撤回している。OpenAI、Softbank、Oracle、UAE の MGX が Stargate という合弁会社(会長は孫正義)を設立し、政権が4年間で最大5,000億ドル(約78兆円)の投資を予定している。データセンターの建設など AI インフラの構築に利用される見込みだ。
業界の中には、高度な AI が人類の存続を脅かすシナリオを警戒し、規制の必要性を訴えてきた人々がいる。トランプ新政権で大きな役割を担うイーロン・マスクもその1人だが、彼は新政権の規制について特に目立った発言をしていない。新しい政府が AI を監督するか、どう監督するかに関してはまだ判然としない部分もある。

AI の活用で遅れを取っているとされる日本でも、データセンター拡充の動きが始まっている。ただ拡充を進める際には、費用面のみならず、データセンター用地の確保、地元住民からの同意を得られるかという論点が出現するだろう。

暗号資産の規制緩和
第2に、暗号資産の規制緩和だ。バイデン政権とは異なり、当局が暗号資産の投資家や開発者に対する監視を緩めることはほぼ間違いなく、新しいコインが数多く誕生するだろう。
業界全体や関心の高い消費者からは、規制緩和が好意的に受け止められると予想される。2024年1月にアメリカで解禁されたビットコインETF(上場投資信託)が、トランプ勝利後に上昇を見せたことからも、市場における楽観論の広がりは明白だ。
日本を含むアジア圏でも、トランプ政権の動きに追随する形で投資対象としての暗号資産を積極的に受け入れる兆しが見られる。ただ、市場での楽観視とは裏腹に、暗号資産の保有者と非保有者の間で経済的な格差が拡大し、不満や怒りが表出する可能性は否定できない。

ソーシャルメディアの変化とビッグテックの政治力
第3に、ソーシャルメディアの変化だ。すでにトランプ大統領は、「政府による検閲」を終わらせるという主旨の大統領令に署名し、プラットフォーム上のファクトチェックや誤情報の削除といった取り組みを後退させている。
加えて、Facebook を傘下に持つ Meta のマーク・ザッカーバーグCEO、X のイーロン・マスクらが政権に近いことで、政治的・社会的な調査にもリスクが生じるかもしれない。
クイーンズランド工科大学のティモシー・グラハム准教授は、ビッグテックが社会を分断させているかについて調査が必要だが、その調査がビッグテックにコントロールされうると指摘する。
Meta が資金提供し、2023年に発表された研究では、同社のアルゴリズムが「分極化や政治的態度、信念に検出可能な影響を及ぼさない」ことを示したとされた。しかし2024年、マサチューセッツ工科大学アマースト校のチャンダック・バグらの研究チームは、当該研究が実施されていた間、Facebook がアルゴリズムを操作し、より信頼性の高いニュース・コンテンツをフィードに出現しやすくした疑いがあると指摘した。
前例のない力を持つに至ったビッグテックは、新政権と親密な関係を築いている。新たに Meta の取締役に就任したダナ・ホワイトは、大統領選でトランプのプロモーションを主導した人物だ。
単に偽情報が溢れかえるという懸念のみならず、ビッグテックが強大な政治力を発揮することで、そもそもソーシャルメディアが持つ政治的・社会的な影響力について、信頼性を担保した形で検証することも困難になるリスクがある。
6. DEI
6つ目のポイントは、DEI(DIversity, Equity, Inclusion=多様性、公平性、包括性)だ。
前提として、トランプ大統領就任前から、民間企業の DEI プロジェクトは攻撃されてきた。きっかけは2023年の最高裁判決で、高等教育における人種に基づくアファーマティブ・アクション(積極的差別是正措置)が事実上終了したことにある。
本件は、大学入学における人種を考慮した措置と憲法解釈の問題であり、直接的に企業の DEI をめぐる取り組みに適用されるわけではない。しかし、最高裁の判決によって、あらゆる場面で人種やマイノリティを考慮した措置に疑問が提起されやすい状況に変わっていた。大手企業や法律事務所の中には、共和党議員のグループから、雇用・昇進などにおいて人種に基づく優遇措置をおこなわないように警告を受けた組織もある。
トランプ大統領は、就任式で「我々は肌の色ではなく、実力主義の社会を築く」と宣言した通り、2023年から続く反 DEI の流れを加速させる狙いだ。主な標的は、性的マイノリティや人種的マイノリティ、および彼らを支援する種々の制度やプロジェクトだ。
たとえば同大統領は、就任初日に署名した大統領令の中で、性別は男性と女性の2つのみを認め、それを変更することはできないとした。これは、保守派が求める見解を反映しているが、近年の生物学的な知見とは相反する。研究では、人間を含む生物の性を固定的な二者択一の概念としてではなく、スペクトラム(連続体)として多様かつ柔軟な位置を取りうると理解すべきだと示唆されている(*3)。
別の大統領令は、全ての政府機関に対し DEI に関わる取り組みおよび役職の廃止と担当職員の「休暇」を命じ、完全閉鎖への足掛かりとした。
(*3)性スペクトラムという概念をめぐる最新の研究動向については、諸橋憲一郎『オスとは何で、メスとは何か? 「性スペクトラム」という最前線』(NHK出版、2022年)に詳しい。
訴訟リスクも
日系企業を含め、DEI プログラムをめぐる各企業の対応は、現時点で分かれている。マクドナルド、ウォルマート、Meta などは直近数週間で DEI プログラムの縮小あるいは廃止を決定した。
トヨタや日産は、トランプ大統領就任前から、多様性を重視する姿勢は維持するとしつつ、活動方針の一部を見直してきた。具体的には、性的マイノリティ支援組織・Human Rights Now が実施する企業平等指数(各企業による性的マイノリティ支援の取り組みなどを調査・評価する制度)への参加取りやめ、各種イベントのスポンサーシップ停止が含まれる。
そうした経営判断に株主が満足するかは不明で、訴訟に発展するリスクもある。2023年には Amazon や Starbucks などが多様性推進の方針をめぐって、投資家に対する義務に違反したなどとして訴えられた。
ただ、株主からの訴訟リスクを警戒して DEI に消極的な姿勢を表明すれば、別のビジネスリスクに直面するだろう。具体的には、優秀な人材や投資を引き寄せる魅力を失ったり、従業員や消費者によるボイコット、場合によっては差別だとして訴訟を受ける可能性もある。
日本の場合、管理職に登用される女性、外国人留学生の国内就職率や定着率、民間企業の障害者雇用率は、政府目標にまで開きがある状況で、DEI の取り組みは遅れている。そのため、トランプ新政権の動きを受けてすぐに DEI の取り組みを廃止するのは得策とは言えないだろう。
DEI をめぐる経営の難易度は、確実に上がっている。すでに触れてきたように、厳密には文脈の異なる司法判断が間接的に企業経営に影響を及ぼすことがあり、特に在米の日系企業は今後も株主や社会的圧力から対応を迫られる可能性がある。
7. エネルギー・環境
7つ目のポイントは、エネルギー・環境だ。トランプ新政権による環境政策は、1期目と似たような方針になるだろう。すなわち、「掘って、掘って、掘りまくれ!」(dril, baby, drill)のスローガン通り、再生可能エネルギーよりも化石燃料の採掘に注力する。
足元でエネルギー価格の高騰に悩まされている日本にとって、アメリカ産の原油や液化天然ガスの生産量・輸出量が増えれば、力強い供給源と位置付けられるだろう。
また、バイデン政権が進めた電気自動車(EV)への補助金(税額控除)をトランプ政権が廃止すれば、トヨタなどの日系自動車メーカーにとってポジティブ材料になる可能性がある。なぜなら、ライバルである中国メーカーや Tesla が EV に注力してきた一方で、トヨタなどはハイブリッド車や水素で動く燃料電池車に投資してきたからだ。

すでにトランプ大統領が署名した大統領令では、EV に対する逆風が示唆されている。2021年のバイデンによる大統領令では、2030年までに新車販売の 50% を EV かプラグイン・ハイブリッド(PHEV)にする目標を据えていたが、トランプはこれを撤回した。
中長期のリスク
一方、国際的な気候変動に対する取り組みは後退し、中長期的なリスクをもたらす可能性がある。
すでにトランプ大統領は、気候変動対策の国際的枠組みであるパリ協定から離脱する大統領令に署名した。第1次政権の2017年に同協定から離脱して以来、2回目の離脱だ。ただ、正式な離脱は1年後の2026年1月に予定されているため、2025年11月にブラジルで開催されるCOP30には、アメリカも締約国として参加する可能性がある。

アメリカのパリ協定離脱による具体的なマイナス要素は、いくつかある。1つは、アメリカが温室効果ガス排出量の年次報告義務を負わなくなり、世界全体の排出量削減に関する進捗状況を把握しにくくなることだ。さらに、気候変動対策の資金が削減されることで、気候変動に脆弱な国家がさらに不安定な立場に追いやられるおそれもある。

クリーンエネルギー投資というメガトレンド
しかしながら、そうした中長期のリスクがありつつも、ニューサウスウェールズ大学シドニー校のウェスリー・モーガン研究員らが指摘するように、トランプ大統領単独で気候変動対策を阻止することはできない。
大きな理由の1つとして、エネルギー投資をめぐるメガトレンドがあげられる。国際エネルギー機関(IEA)が2024年に発表した推計によれば、世界のエネルギー投資額は3兆ドル(約450兆円)を超えているが、そのうち2兆ドル(約300兆円)はクリーンエネルギーとインフラへの投資に充てられている。すなわち、石炭・石油・ガスといった伝統的なエネルギーへの投資は下火になり、その約2倍の金額がクリーンエネルギーに投資されているのだ。
その意味で、化石燃料への依存度が 80% を超えている日本にとって、トランプ政権の方針はリスクにもなりうるし、チャンスにもなりうる。短期的に、トランプ政権の化石燃料推進という方針に追随すれば、クリーンエネルギー投資という波に乗り遅れる。2023年に成立し、今後10年間で官民150兆円超えの投資を促す GX 推進法の展開などが今後の焦点になるだろう。
このように、トランプ2.0がもたらすリスクは多岐にわたる。トランプ政権の不確実性は度々取り沙汰されており、本記事で触れられなかった点も含め、曖昧な予測に終始している点も少なくない。しかし、市場や安全保障、メディア、多様性を取り巻く環境は急速に変化しており、中には日本への影響が予想される領域もある以上、新政権やその周辺で起きる出来事、背景にある動機などをおさえる必要性は変わらないだろう。