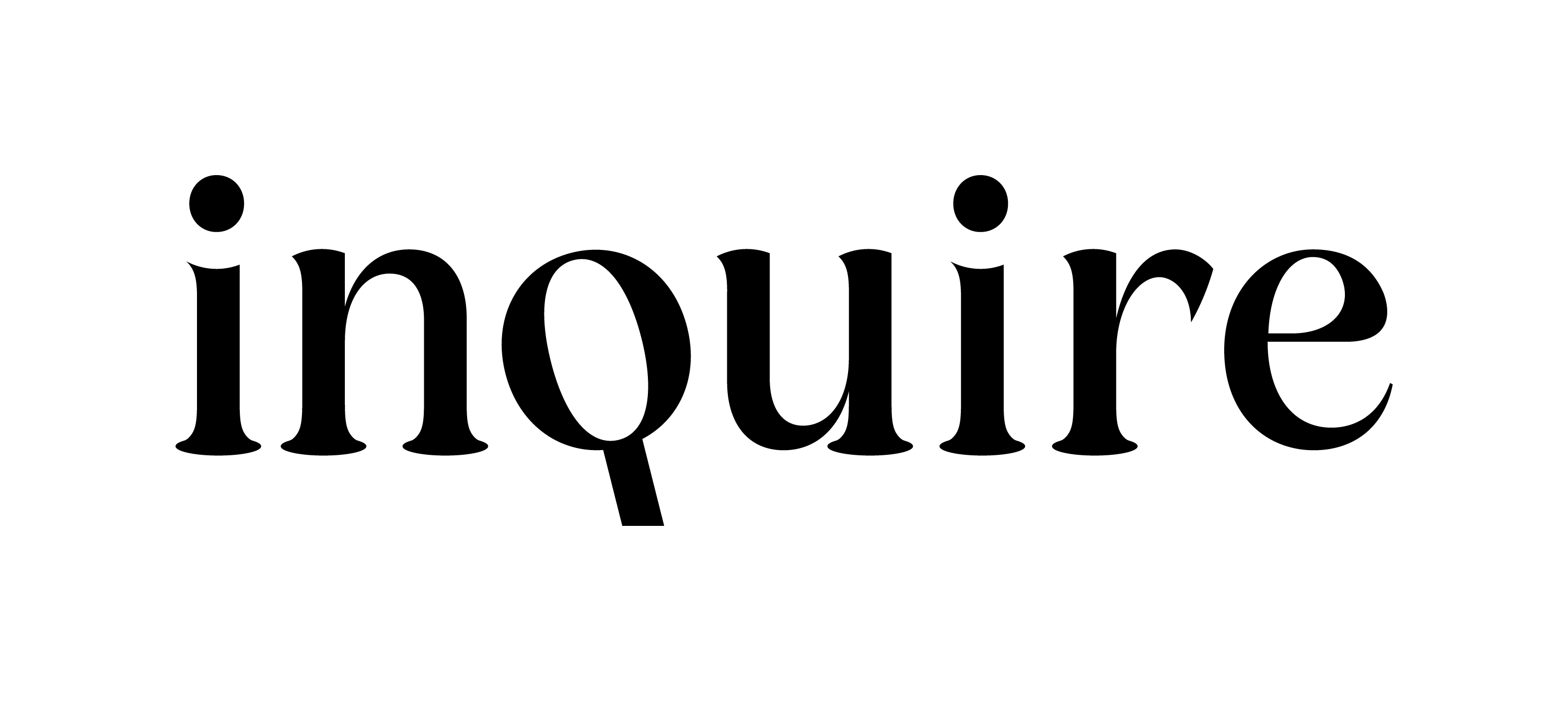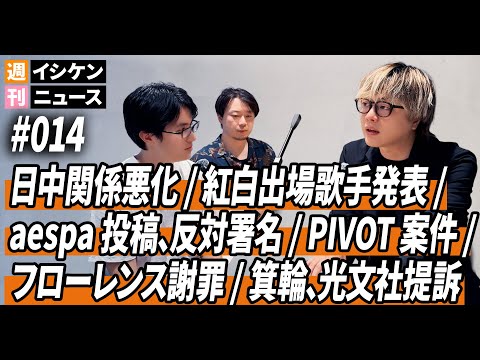⏩ 男らしさや女性蔑視、反フェミニズムなどを奨励するインターネット上の潮流
⏩ トランプ再選に一役買った YouTuber らも関係
⏩ アンドリュー・テイトを数百万人が支持する背景は
本記事はドラマの紹介ではなく、背景にある社会的事象を解説したものですが、一部にネタバレが含まれます。
先月より Netflix で配信されたドラマ『アドレセンス』(Adolescence)が、世界的ヒットとなっている。
同作は、13歳の少年ジェイミーが殺人容疑で逮捕される衝撃的なシーンから始まり、事件の全容を追っていく犯罪ドラマだ。ワンカットで撮影された撮影手法やジェイミー役のオーウェン・クーパーをはじめとする出演者の緊張感のある演技、巧みな構成などで評価を高めている。
すでに「2025年の最も優れ、最も破壊的な番組の1つ」との呼び声も高い。
アドレセンス(Netflix)
そして同時に注目すべき点は、『アドレセンス』の背景にある社会的事象が、世界中に衝撃を及ぼしていることだ。具体的には、世界的なインフルエンサーであるアンドリュー・テイトの存在や、マノスフィアと呼ばれるムーブメントが、若い男性(特にティーンエイジャー)に影響を与えており、ドラマの大ヒットとともに議論を引き起こしている。
マノスフィアの広範かつ強力な影響力
長年インターネット上には、インセル(非自発的独身者)や弱者男性と呼ばれる女性嫌悪もしくは女性蔑視のコミュニティーが存在した。しかしマノスフィアは、それよりも広範かつ強力な影響力を持っているとされる。トランプ当選の背景にある YouTube やポッドキャスト文化とも密接に関係を持っており、今まさに力を増している最中だ。
親世代は、自らの子どもがマノスフィアなどのインターネット上の「有害な文化」に侵されていることを懸念している。英国ではキア・スターマー首相が、『アドレセンス』の制作陣と面会し、現代の子供と親が直面する課題を話し合う事態となった。
彼らの懸念は、決して誇張されたものではない。
過去10年間で、刃物や鋭利な物で殺された英国の10代の若者の数は、240%増加している。文化レベルでは、ネットいじめ、ソーシャル・メディアの悪影響、そして今日の英国の少年たちが直面している計り知れないプレッシャーが問題となっている。男性の怒り、有害な男らしさ、オンライン上の女性蔑視。これは、ありそうな作り話ではなく、避けられない事実だ。
なぜ今、世界中でマノスフィアが話題となり、少年への影響が懸念されているのだろうか?
マノスフィアとは何か
マノスフィアは、男らしさや女性蔑視、反フェミニズムなどを奨励するインターネット上の潮流だ。この中には、次のような多様なグループが含まれている。
男性の権利活動家(MRAs、Men’s Rights Activists) – 「男性差別」の是正を掲げ、離婚や親権、兵役などの領域で「男性が不当に扱われている」と主張する人々。フェミニズムに強く反発し、男性の権利擁護を訴えている。
インセル(非自発的独身者) – 恋愛や性的関係を望んでいるにもかかわらず、それが得られないことで不満と怒りを募らせる男性のコミュニティ。失望を女性への憎悪に転化させる傾向があり、女性を侮蔑・非人間化する極端な言説を共有する。一部の過激派は、オンライン上で女性に対する暴力を称賛し、現実に無差別殺傷事件を起こした例もある。
MGTOW(Men Going Their Own Way) – フェミニズムによって "堕落" した "女性中心社会" からの分離を主張し、結婚などあらゆる女性との関係を避けるべきだと考える人々。異性愛関係を完全に拒否する人々から、恋愛や金銭的な関係を避けてカジュアルなセックスのみを許可する人々などに分かれる。
ナンパ師(PUA: Pick-Up Artists) – ナンパ術や恋愛工学を指南するグループで、女性を「攻略」や「征服」の対象とみなすことが多い。フェミニズムへの強い否定と男性優位な振る舞いが称賛され、女性を意のままに扱うテクニックの共有に重点が置かれる。
これらのグループ間に統一した教義は存在しないものの、男性性の誇示や女性嫌悪(ミソジニー)、反フェミニズム、女性に対する暴力の賛美などで共通している。

後述するように、近年のマノスフィアはインターネットでの影響力を強めている。Reddit や 4chan などの掲示板、ポール・エラムが主催するサイト「A Voice for Men」や「Return of Kings(閉鎖済)」のような個人サイト、YouTube やポッドキャストが主な活動拠点だ。
A Voice for Men
インターネット文化においては、長年にわたって女性蔑視や反フェミニズムの潮流が存在した。しかし、いまマノスフィアに注目が集まっている理由は、こうした長年の文化的背景と現代特有の状況が結びつき、強烈な力を持っているからだ。若い男性は、この過激なコンテンツに「高い割合で接触している」と指摘される。

インセルとの関係
過去数年間、主要メディアで注目を集めていたのは、マノスフィアではなくインセルという言葉だった。
インセルとは「不本意の禁欲主義者」や「非自発的独身者」と呼ばれ、involuntary(不本意)と celibate(禁欲)をあわせた造語だ。「自分たちは、遺伝子のくじ引きの負け組で、なすすべがほとんど無いと主張する、怒りを抱えた男性たち」を指す。日本のネット上の文化で、弱者男性や非モテなどと形容される男性像と近しいかもしれないが、後述するように各国のネット文化の発展と密接に関わってきた。
インセルに関する懸念は、10年以上前から指摘されてきた。
代表的なものが、2014年5月にカリフォルニア州で起こった銃乱射事件だ。6人を殺害した犯人のエリオット・ロジャーはインセルを自認しており、事件直前には自らを拒絶する女性と、性的に活発な男性を罰したいという動機を明らかにしていた。また2018年にカナダ・トロントで起こったアレク・ミナシアンによるテロ攻撃も、インセルとの関係が指摘されている。
インセルとマノスフィアの共通点は多いものの、マノスフィアの一部のグループには、経済的・社会的成功や肉体改造などによって、自らの "不遇" を脱しようと考えるグループも存在し、異なる思考パターンも見られる(*)。「なすすべがほとんど無い」と考えるインセルに対して、マノスフィアの「ナンパ師」のように、主体的に状況を変えようという "前向きな教え" を授けるグループもいる。
PUA(ピックアップ・アーティスト)は、特別なテクニックを学べば女性を性的に征服〔訳註:多くの女性と関係を持つこと〕できると信じている。一方で、インセルは、自らが孤独と苦しみに運命付けられていると考えており、この違いがインセル文化を特に憎悪に満ちたものにしている。
このように、マノスフィア内部にも対立する思想や主張があること、コミュニティ内部の移動があること、ホワイト・ナショナリストなど過激化の入り口として機能している可能性があることなども、重要なポイントだ。
(*)ただし両者は、根本的には女性を性的モノ化(客体化)するものとして扱う点で共通している。この概念の論争性については、江口聡「性的モノ化と性の倫理学」『京都女子大学現代社会研究』、2006年などを参照。
何を主張しているのか?
多様なグループの集まりであるため、マノスフィアに固有の教義は存在していない。ただケイトリン・デューイが指摘するように、その主張は大きく次の2つにまとめられる。
-
フェミニズムは、自然や生物学、そして本来の性差に反して現代文化を支配・腐敗させており、
-
男性は、超支配的で極端に男らしい性役割を受け入れることで、女性を魅了し(あるいは、社会全体を救い)最終的に女性を従属させることができる。
若い男性の悩みに呼応
これらは、反ポリコレや反フェミニズムを主張する、伝統的な差別主義の一形態のように思える。しかしポイントとなるのは、その教義が、若い男性にとっての現実的な悩みと親和的であることだ。
たとえばマノスフィアの有名な教義には、「女性の80%が男性の20%に惹かれる」という『アドレセンス』にも登場したセンテンスがある。これは、男性に「女性が世界を支配している」という誤った信念を植え付けるだけでなく、男性が感じている生きづらさや孤独、疎外感、傷つきやすさの "原因" を解き明かすような魔力となっている。
マノスフィアが訴求力を持っているのは、恋愛での拒絶、疎外感、経済的失敗、孤独、そして将来への希望の乏しさのもとで生きる若い男性たちの現実に語りかけているからだ。
しかし、男性の疎外感の原因をどのように診断しているかが重要な問題だ。マノスフィアは、その原因をフェミニズムの影響に固執させており、男性が直面する困難の増加を、女性が経験している社会的・経済的・政治的な成功と対比させている。このゼロサム〔訳註:誰かの利益を他者の損失とみなすこと〕的な主張は、「女性のエンパワーメントは、必然的に男性の力を奪うことになる」と位置づけ、その証拠として、生物学や社会経済学に関する単純化された、あるいは疑似科学的な理論を用いている。
ネット文化との親和性
またマノスフィアは、インターネット掲示板 4chan や ソーシャル掲示板の Reddit などで見られるネットスラングを多用する。
たとえば「Get back in the kitchen, Make me a sandwich.(キッチンに戻って、サンドイッチをつくれ)」は、女性をからかったり罵倒する際に用いられる。
「Women are property.(女性は財産だ)」は、女性が男性に所有される存在であるという、家父長制に根差した価値観を露骨に示した表現だ。「Your body, my choice(お前の身体は、俺が決定する)」は、女性の身体の自己決定権を謳った「My Body, My Choice.」を揶揄したものだ。
こうしたスラングは、単なる揶揄や罵倒として機能しているだけでなく、マノスフィア内部のコミュニティの結束を強化して、コミュニティが敵だとみなす人々への犬笛(特定のコミュニティにしか理解できない表現で、敵対者などへの攻撃を煽る手法)としての役割がある。
マノスフィアは、どのように台頭したのか
マノスフィアが誕生する以前、男性の権利を擁護するような運動には、長い歴史が存在した。
男性解放運動(MLM)
サイバー犯罪とジェンダーの専門家であるリサ・スギウラは、1970年代初頭に起源のある男性解放運動(Men’s Liberation Movement, MLM)が、ウィメンズ・リブ運動(WLM)と共に生まれたと語る。当時 MLM は、フェミニズムの同盟者として、男女双方が厳格に押しつけられてきた性役割(ジェンダーロール)によって生じる被害に対して、共通認識を持っていた。
ジェンダーロールによる男性の苦しみについて、(時代はくだるものの)よく知られているのが、ヘゲモニックな男性性(覇権的男性性)という概念だ。これは R.W.コンネルによって提示された概念で、家父長制社会が女性だけでなく男性も苦しめることを示唆している。(*)
ヘゲモニックな男性性とは、たとえば西洋社会において、白人・異性愛者・中流階級の男性が「支配的」になりやすく、黒人などの有色人種や同性愛者、労働者階級などの男性が「従属的」になる男性のあり方を指す。
従属的な男性も、支配的な地位にあるヘゲモニックな男性性を称賛するだけでなく、女性もまたヘゲモニックな男性性を理想像とすることで、その「男らしさ」はますます優位な地位に押し上げられる、という仕組みだ。つまり、男性と女性という二項対立的に捉えたジェンダーの中で、男性が優位になるだけでなく、男性の中にある階層性もまた男性優位社会を強化しつつ、男性自身を苦しめる構造となっている。
この概念が示すように、フェミニズムは女性の権利擁護としての側面のみならず、男性の「生きづらさ」を検討する側面も持っており、MLM はそうした立場に呼応した形だ。

MLM から MRM へ
スギウラによれば、1970 年代後半までに MLM は解散して、一部の論者は、反フェミニストを掲げる男性の権利運動(MRM)へと変貌した。彼らは、現代社会が「女性化」したことで様々な問題が生じたと考え、伝統的な男性的価値観への回帰を訴えはじめた。
当時影響力を持った研究の1つが、ウォーレン・ファレルによる『The Myth of Male Power』(*)だ。ファレルは、公的領域(政治や労働市場などの領域)と私的領域(家族や恋愛などの領域)を区分した上で、私的領域では女性が支配的であり、男性が差別的な位置にあるとする。ファレルは、男性が過度の社会的・経済的権力を持っているという広く知られた認識は誤りで、男性は多くの点で体系的に不利な立場に置かれていると主張する。
その後もファレルは、子どもの親権をめぐって男性が不利な立場にあることや父親というロールモデルの不在による子どもへの影響などを通じて、男性の権利擁護を展開していく。
ファレルは、議会や企業の取締役会の大多数が、男性によって構成されていることを否定しない。しかし彼は、その事実によって、多くの男性や少年たちが直面している問題に、十分な注意が払われていない現状が覆い隠されてしまっていると述べる。たとえば、家庭裁判所制度によって父親が子どもと引き離されることが多いこと、大統領府に「男性と少年に関する評議会」が存在しないこと、そして大学に「女性学」はあっても「男性学」の学部が存在しないことなどだ。
ただ注意すべきは、ファレルのような研究と女性蔑視的な言説が横滑りし合う懸念は、常に存在したことだ。
1980年代には、シスジェンダー(生まれ持った性別と自認する性が一致している人)の白人男性の社会的地位が低下しているという認識や、フェミニストや多文化主義などの運動が主流な政治勢力として台頭していることに危機感を持つ人々が、反フェミニズムの旗印に結集しはじめた。
(*)Raewyn Connell. Masculinities. 1995. Allen & Unwin
(*)Warren Farrell, The Myth of Male Power, Simon & Schuster, 1993
インターネットの周縁から中心に
現代のマノスフィアの性質を決定づけた出来事は、インターネットの登場とオンライン・コミュニティの形成だ。
オンラインにおける女性蔑視を専門とするエマ・ジェーンは、マノスフィアが「サブカルチャー的な荒らしコミュニティ、過激な男性権利擁護団体、そしてナンパ師が融合」した「キメラ的な運動体」だと述べる。ジェーンは、マノスフィアの参加者たちが「負け犬のアウトサイダー」という自己アイデンティティを強く持ち、反体制、反リベラル(左派)、反道徳的保守主義、反聖職者的傾向、リバタリアン擁護などの傾向があるという。
彼らは、2010年代半ばまでにオンライン・コミュニティでの地位を確立し、存在感を増していった。2014年の GQ 誌には、次のような記述が見られる。
君は、男性権利運動に加われる男だろうか?
おそらく無理だ――少なくとも、我々の "女性化した社会" によって "男性という種" が深刻な危機に瀕していると確信している、怒れる活動家たちの増加を前にすれば。
彼らが言うには、今は「女性の時代」だ。性的関係でも、大学でも、親権争いでも女性が優位に立っているという。そして、いわゆる「でっちあげられた」レイプ事件の話なんてしようものなら怒り心頭だ。そんな現状が、ある種の男性にとって革命に加わる理由になっている。
2017年、Blogosphere(ブログ圏)から生まれた Manosphere(男性の世界、マノスフィア)という言葉をタイトルに冠した『マノスフィア:男らしさへの新たな希望』が出版された。また同年には、オルタナ右翼の差別主義者と考えられていた男性犯罪者にマノスフィアの影響があったことが The New York Times 紙で指摘された他、2016年の Guradian 紙にレッド・ピルに関する言及があるなど、主流メディアからの注目も高まった。
レッド・ピル
ここで言うレッド・ピルとは、1999年の映画『マトリックス』に登場する赤い薬のことだ。レッド・ピルを飲めば、安定した人生が根底から覆るような「苦痛の真実」を知ることができる一方、ブルー・ピルを飲めば、真実は知らないままだが、満ち足りた「甘美な人生」を送ることが出来る。
マノスフィアの世界観におけるレッド・ピルとは、「女性が責任を負わずに世界を運営し、その被害者である男性は、苦情を言うことすら許されていない」という "真実" に気付くことだ。
マノスフィアの特徴は、反フェミニズムなどの個別の論点を主張するというよりも、「フェミニズムやリベラルな価値観に洗脳された社会」そのものを攻撃することだ。そのため幅広い陰謀論を通じて、その他の過激主義や差別主義に結びついている。
ピル(錠剤)の比喩は、オルトライト(極右勢力)にも取り入れられており、フェミニズムが世界を支配しているという主張から、得体の知れない世界的エリートが世論を操作しているという陰謀論に至るまで、横断的な言説となっている。
こうした世界観は、ドナルド・トランプの再選にも影響を及ぼしたと言われる現在のマノスフィアにも引き継がれている。たとえば副大統領のJ.D.ヴァンスは、トランプの批判者であった自身が、その支持に転向した背景をレッド・ピルを飲むことに喩える。
J.D.ヴァンスがレッド・ピルについて語る背景なども記された書籍『カウンターエリート』が、4月18日に発売されます。Amazon など各種サイトより、ぜひ予約ください。
なぜ中心に?
マノスフィアの影響力が伸長した背景には、間違いなくインターネットの成長がある。しかし複数の専門家は、それだけが要因ではないと指摘している。
たとえば過激主義を研究するアリサ・チェルウィンスキーは、2020年以降の新型コロナによるロックダウンが影響を与えたと考える。
現在、私たちが目にしているのはロックダウン、そして孤立による影響だ。テクノロジーの使用が増えたことで、若い男性たちにとって、孤独感や疎外感を加速させる引き金になっている。
一般的に男性は、孤独やうつ病、自殺などの精神衛生上の問題を抱える割合が高く、それらは増加傾向にある。マノスフィアのインフルエンサーは、自らがそうした身近な悩みの処方箋を持っているように語りかけている。コロナ禍を通じて加速した、男性のメンタルヘルスの問題に、マノスフィアが応えることが出来た側面は否定できないだろう。

加えて、マノスフィアによるコンテンツは、YouTube や TikTok などのアルゴリズムで拡散されやすい特徴がある。差別的な言説が本質的に拡散性を持っているのか、あるいはマノスフィアのコミュニティが、そうしたコンテンツのエンゲージメントを高めているかは分からないが、ソーシャルメディアとの相性が良いことも問題を加速させているのだろう。米国の大統領選後には、女性蔑視のコンテンツが増加しているとの報告もあり、オンラインの「マノスフィア化」が進んでいる可能性は高そうだ。
トランプ2.0のキーマン
そうした中で、2024年のトランプ再選にマノスフィアが一役買ったことは、多くのメディアが報じている。
たとえばジャーナリストのブライアン・バレットは、次のように記す。
トランプは、彼ら〔訳註:YouTuber やポッドキャスター〕と数時間にわたって対談し、数百万人の保守層や政治に無関心な人々に訴えかけ、自らがコミュニティの一員であること、"シグマ(孤高の存在)" であること、影響力を持つ人物であること、そして名声そのものを美徳とする男性像の頂点にあることを印象づけた。2016年や2020年の選挙に関心を持っていなかった、ニュースを主にソーシャルメディアから得る若い世代にとって、それがトランプとの最初の本格的な出会いでもあった。
たとえば、著名 YouTuber のテオ・フォンの番組に出演したトランプは、自らの銃撃事件や格闘家、アルコール(トランプはアルコールを飲まず、タバコを吸わない)、ロビイスト、ヘルスケアなどの雑多な話題について語り合っている。
テオ・フォンは、後述するマノスフィアの中心人物、アンドリュー・テイトが男性の孤立感や苦悩という重要な話題を提起していると好意的に評している。また「伝統的な男らしさ」こそが秩序ある社会の鍵だと主張するジョーダン・ピーターソンをゲストに招いたこともある。
こうしたインフルエンサーとトランプの会話は、これまでの選挙キャンペーンでは考えられないくらいにカジュアルだ。格式張った政策の話はほとんどしないまま、スポーツや格闘技、ライフスタイルなどのプライベートな話題の合間に、移民政策の話題が差し込まれる。
これは現代のマノスフィアというよりも、マノスフィア的な世界観とも親和的な YouTuber やポッドキャスターにとって一般的なスタイルだ。彼らの中には、直接的な差別主義あるいは男性優位主義的な発言を厭わない者もいるが、多くが慎重な言葉遣いを選ぶ。たとえばアンドリュー・テイトについて「彼が言うことのすべてに賛成するわけではないが…」といった具合だ。
4chan や Reddit がサブカルチャー的な空間だとすれば、いまのマノスフィアの言説を牽引しているのが YouTube や TikTok などの主流なソーシャルメディアだ。そのインフルエンサーたちは、一見すると(露骨な差別主義者よりは)穏当な語り口で、男性性の誇示や女性嫌悪(ミソジニー)、反フェミニズムなどを勧めてくる。
こうした点も、若者がマノスフィア的世界観に引き込まれる一因となっている。
アンドリュー・テイトとは何か
そうした現代のインフルエンサーが、ほぼ必ず言及するマノスフィアの帝王が存在する。アンドリュー・テイトだ。
1986年生まれのテイトは、キックボクサーとしてキャリアを開始した後、「ハスラー大学」や「リアルワールド」などのオンライン・サロン運営などで注目を集めた。
動画やチャットサービスを通じたサロンで、テイトはマーケティングやEC、暗号資産などで金儲けをする方法、自己啓発、そして女性と関係を築く方法などを教えていた。またサロン運営などで築き上げた資金によって得たジェット機や高級車、数々の贅沢品を顕示することで、テイトは瞬く間に "成功者" としてのイメージを築きあげた。
テイトは、「女は男に従うべきだ」や「うつ病は甘えだ」といった過激な主張と、一攫千金的なノウハウをアピールすることで、多くのフォロワーを獲得した。TikTok の動画は、彼が追放される以前には116億回以上も視聴され、Instagram では470万人ものフォロワーを獲得していた。
こうして彼は、「セックスや身体的暴力、絞めつけによって女性を支配・服従させる方法について、ネット上で長々と語る」ことで、「男性性の帝王(The King of Masculinity)」や「アルファの帝王(The Top G)」に上り詰めた。
民事・刑事訴訟
テイトは、人身売買や未成年者との性交などの容疑で、繰り返し民事・刑事訴訟に直面している。また大半のソーシャルメディアからは女性蔑視などの発言によって追放されており、例外はイーロン・マスクによって買収された Twitter(現在のX)のみだ。現在、テイトの X アカウントは、1,000万人以上のフォロワーを獲得している。
しかしテイトを取り巻く状況は好転している。今年2月にテイトは身柄を拘束されていたルーマニアで釈放され、米国に戻ってきた。背景にはトランプ政権からの圧力があったとも報じられており、再びオンライン・コミュニティの覇者となる可能性も高い。
何百万人もの男性が支持
しかしマノスフィアが台頭した原因は、すべてテイトに帰されるわけではない。
テイトとマノスフィアは、自然発生的に現れたわけではない。それは、若い男性が直面しているより深刻な一連の課題の兆候なのだ。これらの問題は、テイトのような人物をプラットフォームから排除するだけでは解決しない。短期的にはこうしたことが必要になる場合も多いが、より賢明なインフルエンサーが必ず現れ、同じ根深い問題に対応し、先人たちの失敗を避けながら、より効果的な戦術を採用するだろう。
何百万人もの男性がテイトを支持していることは、男性をめぐる危機が顕在化していることを示唆している。
男性性研究で知られるマイケル・キンメルは、男性が屈辱感を抱いていることに注目する。「自分が権利を持っていると感じながら、期待していたものが得られなかったら、それは屈辱感を生む原因」となり、そのことが男性を極右グループに参加させたり、銃乱射事件に駆り立てていると考える。
つまり、アンドリュー・テイトなどのインフルエンサーは、現象の「原因」ではなく「結果」の一部に過ぎないのだ。
女性からの支持
加えてマノスフィアは、一部の女性からも支持を得ている。トラディショナル・ワイブズ(伝統的な妻たち)の略称であるトラッド・ワイブズ(trad-wives)は、伝統的な家庭の価値観を支持・実践する女性たちだ。彼女らは、稼ぎ手としての男性と主婦としての女性という性役割(ジェンダーロール)を称賛し、フェミニズムを否定する傾向にある。
また、レッドピルを飲んで「フェミニズムは存在すべきではない」という真実に気づいた女性、レッドピル・ウーマンも存在する。彼女たちは、伝統的な女性らしさを支持しつつも、社会的地位や経済的安定、「価値の高い」パートナーへのアクセスなど、女性らしさのプレミアムを獲得するための戦略的交渉を積極的におこなっているとも言われる。
ヘゲモニックな男性性という概念が示唆するように、マノスフィアは単なる男性の女性蔑視のみから理解されるべきではない。時に、女性も特定の男性性を称賛することで、社会的な規範が形作られているのだ。
日本におけるマノスフィア
日本でマノスフィアに関連したコミュニティが存在するかは、まだよく分かっていない。2015年頃に「恋愛工学」の概念を広めた藤沢数希や、X などでコミュニティを形成するナンパ界隈、「真の弱者は男性」や「女性をあてがえ」などの主張で知られる弱者男性論など、類似する概念はいくつか見られるものの、研究の進展が待たれる分野だ。
ただこの中でも、弱者男性論の形成と変容は、マノスフィアとの類似性が見られるかもしれない。
伊藤昌亮によれば、弱者男性はモテない(恋愛弱者)、職がない(経済弱者)、うだつが上がらない(コミュニケーション弱者)という3つの属性で定義され、1990年代はオタクが象徴的な存在とみなれていた。彼らは、2ちゃんねるやはてなダイアリーなどのオンライン・コミュニティで、議論と交流を深めていった。(*)
こうしたオンライン・コミュニティでの議論は、「女神化志向」と女性への攻撃や誹謗中傷というアンビバレントな形で顕在化したミソジニーとなり、その後、反フェミニズムや反リベラルという論点と結びつき、弱者男性の階級闘争としての側面を見せていく。最終的に、レイシズムやジェンダーバックラッシュなどとも手を取り合い、このコミュニティの参加者は、新自由主義的なイデオロギーを内面化するに至っていくと伊藤は述べる。
日本固有の事情がありながらも、オンライン・コミュニティでの議論や結束を経て、独自の文化を構築したという意味で、マノスフィアとの共通点は多そうだ。
現時点で、日本にアンドリュー・テイトのような強力なインフルエンサーは見当たらない。しかし、ナンパ手法を教授するリアルナンパアカデミーと名乗るコミュニティから、準強制性交等容疑などで複数の逮捕者が生まれる事件なども生じている。またナンパや「男磨き」を教授する YouTuber(たとえばABEMAの番組などに出演するジョージ)も存在しており、国を超えた潮流として顕在化していくことは、十分に考えられる。
こうしたコミュニティが全て害悪であるのか(たとえば、有害な男性性という概念の妥当性なども含め)は、議論が残るだろう。しかしマノスフィアが、憎悪犯罪や過激主義への入口になっているとも指摘される中、そのコミュニティの形成・発展を慎重に観察する必要があることも事実だ。
(*)伊藤は、当時の弱者男性論の性質を「ブロゴスフィアとしての非モテ論壇の中のものと、匿名掲示板としての2ちゃんねるの中のものとがあった」と分類する。日本でも、Blogosphere(ブログ圏)と男性論の結びつきが重要であったことを示唆する指摘だろう。
マノスフィアが、本当の問題なのか?
ガーディアン紙のマイケル・ホーガンは、親たちが『アドレセンス』に恐怖する理由を的確に指摘する。
私たちは、子どもたちに道路の渡り方や知らない人と話してはいけないことを、念入りに教える。しかし、インターネットの使い方については、ほとんど教えない。
親たちが思い描く「子どもたちの健全な日常」と、実際に子どもたちがオンラインでやっていることの間には、しばしば大きなギャップがある。親は「Roblox〔訳註:オンラインゲームのプラットフォーム〕で遊んでいる」と思っていても、実際には Reddit を見ていたりする。親は「宿題をしている」とか「友達と無邪気にメッセージをやり取りしている」と思っている。でも、現実にはポルノを見ていたり、あるいは刑事のフランクが端的に表現したように、「あのアンドリュー・テイトのクソ動画」を見ている。
ただし『アドレセンス』によるマノスフィアの描写が、問題の所在を見誤らせるのではないかとの批判もある。ジャーナリストのエド・ウェストは、英国におけるナイフ犯罪の大半は、『アドレセンス』で描かれた「父親を持つ、若い白人男性」によるものではなく「父親不在の若い黒人男性」によるものだと指摘する。
そのうえで、次のように述べる。
スターマー〔訳註:英首相〕が取り組もうとしている社会問題は確かに存在している。ただし、それは観客にとって心地よく感じられるような形ではない。(略)
政治家たちが問題に効果的に対処できない一因は、フィクションを見過ぎており、現実を半ば物語的に捉えるようになってしまっているからだ。彼らは直感的に、「稀な悲劇的ケース」―― 脚本家が好んで取り上げるテーマ ―― に意識が向きがちであり、社会全体の肯定的な結果を増やすという視点が欠けている。
こうした見解は、殺人を犯す子どもには「貧困環境や計画性、暴力の前歴、女性に危害を加える意志を示す明確な兆候」があり、それはマノスフィアとの関係ではないと主張するコナー・フィッツジェラルドや、イアン・レスリーによる次の指摘とも共通している。
若い男性によるミソジニーやミソジニスティックな暴力の潮流が高まっていること、あるいは、現実世界の犯罪や軽犯罪をオンライン文化に結びつけることの強い証拠を見つけるのは、驚くほど困難だ
ウェストやレスリーのような論者は、若い少年が置かれている状況を『アドレセンス』のように分かりやすいドラマで解釈したり、軽率にマノスフィアと結びつけることに警鐘を鳴らしている。それは問題の焦点を見誤らせ、議論を混乱させる懸念があるという。
ソーシャルメディアへの禁止措置?
魅力的な物語のつくり手が、必ずしも適切な政策決定者になれるわけではない。『アドレセンス』の脚本家ジャック・ソーンは、10代の若者に対するソーシャルメディアの規制を強化すべきだと考えているものの、禁止措置は有効であるという証拠が限られており、その実施も現実的でないと指摘されている。
専門家からは、オンラインの安全教育の強化、時代遅れのガイドラインの見直し、教師や親、若者らの適切なサポートの重要性が指摘されている。
こうした議論を概観することは、現代においてマノスフィアが危うい存在であることを示唆するだけでなく、それだけに注目することで、広範な社会的課題の原因や対処法を見誤ることの危険性を示唆している。ただ少なくとも、日本においてオンライン・コミュニティの危険性や子どもにもたらす有害性が、十分に周知・議論されていないことも重要な論点であるだろう。