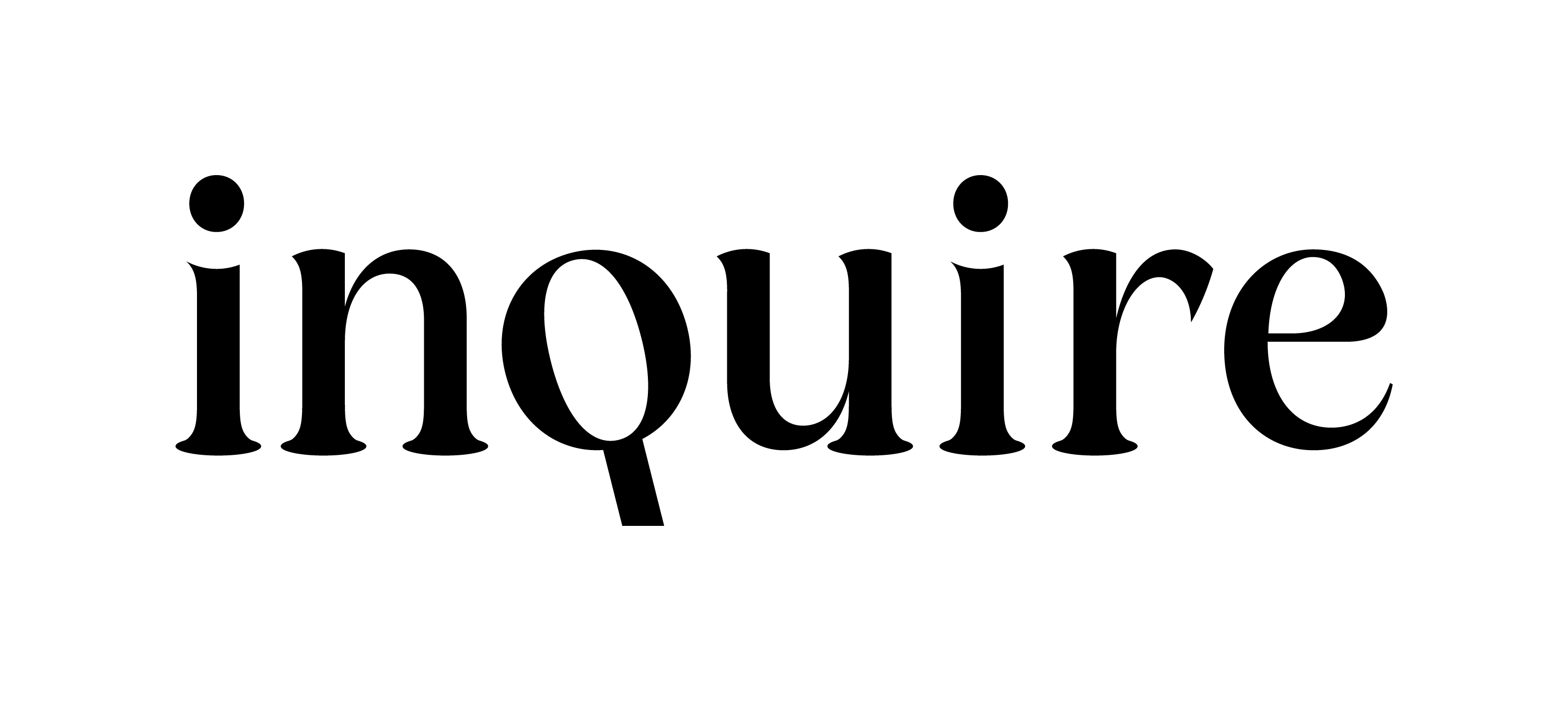台湾・鴻海精密工業会長、日産との協業目指す = 経営危機の背景
公開日 2025年02月12日 15:31,
更新日 2025年02月12日 17:04
日産の経営再建をめぐって、台湾・鴻海精密工業の劉揚偉会長は、ロイターの取材に対して買収ではなく協業を目指していると明らかにした。先週、日産はホンダとの経営統合を白紙にしたい意向を表明しており、同社の行く末は不透明なままだ。
背景説明(β版)
免責事項:以下の背景説明(β版)は、AI によって一部の執筆・編集がサポートされています。AI による執筆・編集のサポートは、コンテンツ内容の正確性や分析の妥当性を保証しない可能性があります。
日産自動車の財務状況は、ここ数年で大きく改善している。2023年度通期(2024年3月期)の連結売上高は約12兆6,857億円、連結営業利益は5,687億円で、売上高営業利益率は4.5%に達した。営業利益は前年比で約51%増加し、当期純利益も4,266億円と前年度(2,219億円)からほぼ倍増している。長年続いた低迷期(2019–2020年度には巨額赤字)から一転し、コスト削減や販売回復により黒字基調を取り戻した。
しかし、財務面で課題が完全になくなったわけではない。有利子負債は依然として巨額であり、今後数年で償還の山場を迎える。特に2026年には約56億ドル相当の債務の返済期限が集中する見通しで、これは少なくとも過去数十年で最大水準となる。
このため同社は、財務の健全性を保ちながら将来の成長投資(電動化技術など)を賄うという、困難な舵取りが求められている。また日産は、自動車事業単体ではネットキャッシュ(現金が負債を上回る状態)を確保しているものの、引き続き債務管理と収益力強化の両立が経営課題となっている。
主要な経営課題
日産は依然として、複数の経営課題に直面している。主な課題として、競争力の回復や技術革新への対応(特にEV戦略)、そして人員削減を含むコスト構造改革が挙げられる。
まず競争力と市場シェアの低下については、日産は世界各地域で競争力低下に直面している。とりわけ中国市場での苦戦が顕著で、2023年には中国の自動車市場全体が前年より6.0%成長した一方、日産の中国販売台数は前年比24.1%減の約79.4万台に落ち込んでいる。また米国でも販売不振により、市場シェアが低下傾向(2018年に11%あった米国シェアは2022年に6%程度まで低下し、2024年上期は5.8%まで落ち込んだ。
トヨタやホンダ、ヒョンデなどの競合他社に比べ、モデルラインナップの魅力やブランド力で見劣りし、商品競争力の強化が急務となる。
技術革新とEV戦略の遅れについて、日産は2010年に「リーフ」を発売し EV の先駆者となったものの、その後長らく主力 EV がリーフのみで、テスラや中国・BYDなど新興勢力が台頭する中でリーダーシップを失っている。近年ようやく新型EV「アリア」を投入したものの、ラインナップ拡充のスピードで競合に遅れを取っている。EVシフトの波に乗り遅れれば市場で取り残されかねず、経営上最大の課題の一つとなっている。
またコネクテッドカーや自動運転など技術革新の分野でも、プロパイロット等の先進運転支援技術を持つものの、競争相手(テスラのAutopilotやGMのSuperCruiseなど)との競争は激化している。日産は長期ビジョン「Ambition 2030」において、2028年度までに全固体電池を搭載したEVを市場投入する計画を打ち出すなど、技術面で巻き返しを図っているものの、巨額の開発投資とスピードが求められる。
そしてコスト構造改革と人員削減については、ゴーン体制下で急拡大した反動から、日産は生産能力や人員の過剰を抱え、収益を圧迫してきました。このため近年は大胆なリストラが進められており、グローバル生産能力の20%削減と9,000人規模の人員削減を含む再建策が発表されている。実際、生産拠点の再編(例えばスペイン・バルセロナ工場やインドネシア工場の閉鎖)や不採算地域からの撤退(韓国市場からの撤退、ロシア事業の売却など)を実行し、固定費圧縮を図りました。
近年の経営再建の取り組み
上記の課題に対応するため、日産は、コスト削減の断行、アライアンス戦略の見直し、そして組織・ガバナンス改革などの経営再建策を実行してきた。
まずコスト削減と事業効率化については、固定費削減と収益性向上に注力している。2020年中頃には中期経営計画「Nissan Next」を策定し、生産拠点の集約やモデルラインナップの絞り込みを実行しました。具体的には、上述した人員削減や工場閉鎖の他にも、ダットサンなど低収益車種・ブランドの整理などが行われた。
この結果、固定費は大幅に圧縮され、2021年度以降は営業利益の黒字転換とフリーキャッシュフローの改善(2023年度の自動車事業フリーキャッシュフローは、3,230億円のプラス)つながっている。引き続き「選択と集中」を進め、限られた経営資源を電動化技術や主要市場の商品競争力強化に振り向ける方針だ。
またアライアンス戦略の再構築については、ルノー・日産・三菱のアライアンス関係も、この数年で大きく見直された。カルロス・ゴーン氏の逮捕以降、日産と筆頭株主ルノーとの関係が不安定化していたが、2023年に入って両社は、提携条件の見直しで合意した。その内容は、ルノーが日産株の持株比率を現在の約43%から15%へ引き下げ、日産とルノーが対等の15%相互出資関係となるものだ。
この新たな合意により、従来ルノー優位だった資本関係が対等に近づき、日産は経営の自主性を取り戻す一方、引き続き共同開発や購買などで協業を続ける。例えば日産はルノーのEV専門子会社「Ampere(アンペア)」に出資し、次世代のEVプラットフォームやソフトウェアを共同開発する計画だ。
また三菱自動車とも軽EV(サクラとeKクロスEVの共同開発)などで協調を深めており、アライアンス全体で技術資源を共有し競争力を高める戦略が進行している。
そして組織・ガバナンス改革もおこなってきた。元会長の不正問題を契機に、日産は内部統制と経営体制の強化にも取り組んできた。2019年には指名委員会等設置会社への移行(社外取締役を中心とする指名・報酬・監査の各委員会を設置)を実施し、トップの独裁を防ぐガバナンス体制を整備している。また、西川広人氏の辞任を経て内田誠CEOが2019年末に就任し、新経営陣の下で企業風土の改革と意思決定プロセスの健全化が図られた。
さらに、業績連動型の給与体系や取締役会のスキル多様化などガバナンス面の改革も行われており、透明性と説明責任の高い経営体制への移行を目指し、社内外の信頼回復に努めている。