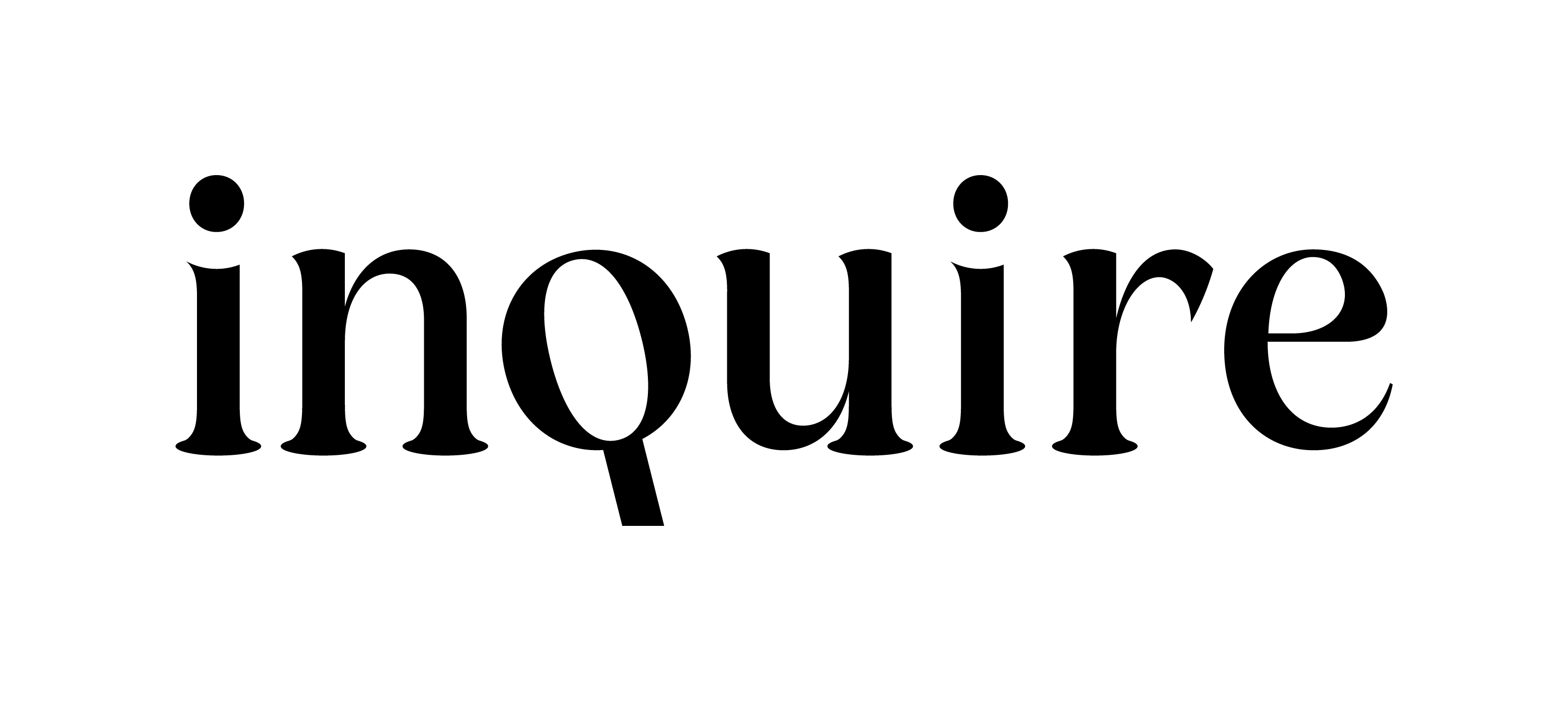東京都が、新築建物に太陽光パネルの設置を義務づける条例改正案を検討している。東京都は年度内の条例改正に向けてパブリックコメントを募集した他(6月24日まで実施)、有識者で構成される東京都・環境審議会も義務化を求める答申をまとめた。
しかし、この太陽光パネルの設置義務化をめぐっては、批判も相次いでいる。ネット上では「住宅価格が上がる」、「電気料金が上がる」、「好きな家を建てる自由もないのか」などの声が上がっている他、「カネ持ちだけが得して、一般国民が負担する『カラクリ』」があるという主張も見られた。一方、住宅メーカーは義務化に前向きだという指摘もあり、ネットの批判について「今の太陽光ヘイトは異様」とする再批判も見られる。
果たして、こうした議論はどれだけ妥当なのだろうか?(*1)
(*1)なお、今回の義務化をめぐっては「太陽光発電の普及そのもの」を批判する立場から反対の声も上がっている。このなかには、太陽光発電の普及による電力供給の不安定化や、いわゆる「再エネ賦課金」の負担増加への懸念など、再エネをめぐる一般的な議論が含まれている。ただし本記事では、義務化にまつわる固有の論点を中心に整理する。
太陽光パネルの設置義務化とは何か?
そもそも東京都が検討する太陽光パネルの設置義務化とは、どのような内容なのだろうか?
東京都は、環境確保条例の改正によって住宅を含む中小の新築建物への太陽光パネルの設置義務付けを目指している(島嶼部は対象外)。東京都は、2030年までに都内での温室効果ガス排出量を2000年比で半減させる目標を掲げており、今回の義務化もこの目標達成の重要施策として位置付けられている。
義務を負うのは大手ハウスメーカーなど事業者
なお、都内の全ての新築物件が義務化の対象となるわけではない。なぜなら、義務を負うのは建物のオーナーではなく、住宅を供給するハウスメーカーなどの事業者で、さらに義務化の対象は、年間の都内供給延床面積の合計が2万㎡を超える事業者に限定されているためだ。
都の試算によると対象事業者数は約50で、都内で年間に着工される物件のうち約半数が義務化の対象となる。また取り組みが不十分な事業者には、事業者名の公表などのペナルティーも検討されている。
事業者の設置義務量は、太陽光パネルの設置容量の「総量」として規定される。つまり、事業者ごとに「年間これだけの太陽光パネルを設置しなくてはならない(発電容量換算)」という数値が設定される。具体的には「事業者の年間供給棟数×85%(パネルの設置可能率)×2kw」で義務量が算出される。
なお設置可能率とは、太陽光パネルの設置に適さない建物を考慮したもので、85%という数字は「都内では平均85%の建物が太陽光発電に適している」という都の試算に基づいている。
日本では初も、海外では義務化の動き
条例改正が実現すれば、こうした義務化は日本初の試みとなる。昨年、政府も国レベルでの義務化を一時検討したが、結果的に早期の導入は見送られた。また京都府は、条例によって一定規模以上の建物を建築する場合に、再生可能エネルギーの導入計画書の提出を義務付けている。しかし、太陽光パネルの「設置」の義務化を検討しているのは、今回の東京都が初めてだ。
ただし、海外ではすでにこうした事例が存在する。米カリフォルニア州は2020年より新築建物に太陽光パネルの設置を義務付けている。またドイツでも一部の州で、新築住宅での太陽光パネルの設置が義務付けられている。EUも、新築建物への太陽光パネルの設置義務化を現在、検討している。
なぜ設置義務化は必要?
では義務化によって、どのようなポジティブな効果が期待されるのだろうか?
環境法学を専門とする東京大学の高村ゆかり教授をはじめとした有識者で構成される都の環境審議会は、今回の条例改正が求められる背景を3つの観点から指摘している。
1. エネルギー安全保障
1つは、エネルギー安全保障の観点からの必要性だ。現在、日本はエネルギー源の85%を輸入が必要な化石燃料に依存している。そのため必要なエネルギーについて合理的価格で継続的に確保すること、いわゆるエネルギー安全保障におけるリスクが大きいとされており、特にウクライナ情勢を受けた調達環境の不安定化によって、その懸念はますます顕在化している。
関連記事:経済安全保障とは何か?米中対立と新たな担当大臣により注目
実際、最近の日本では電力ひっ迫注意報が繰り返されており、電力およびエネルギー不足は国民的な関心事となっている。
関連記事:なぜ政府は節電を呼びかけているのか?電力使用制限令や需給ひっ迫警報とは
そのため、今後は脱炭素に加えて、エネルギー安全保障の観点からも、利用するエネルギーを「減らす」「創る」「蓄える」取り組みが必要であると、環境審議会は指摘している。こうしたエネルギー安全保障の観点で太陽光発電の普及を重視する姿勢は、最近のEUのエネルギー戦略などでも見られている。
2. 脱炭素の取り組み
環境審議会が次に指摘するのが、脱炭素への取り組みの重要性だ。現在、世界各国は世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて1.5℃に抑えることを目指している。しかし、今年発表されたIPCC(気候変動に関する政府間パネル)の報告書は、現状ではこの目標達成が不可能であると警鐘を鳴らしている。
温暖化を抑制するための温室効果ガスの排出削減に向けて、太陽光発電などの普及は重要な役割を担うとともに、東京都としてもゼロエミッション戦略を実現していきたい考えだ。
関連記事:カーボンニュートラルとは何か?(前編)日本、2050年までの脱炭素社会を宣言
ビジネス上の利点
最後に挙げられているのが、企業の脱炭素への取り組みが投融資や取引の条件となりつつあることだ。世界では金融市場を中心に、気候変動リスクへの対応を投資先や取引先に求める動きが強まっている。日本でも東京証券取引所がプライム市場の上場企業に対して、気候変動に関する情報開示を求めはじめた。
したがって、建物を所有する企業が太陽光発電を導入し脱炭素化に取り組むことは、事業活動の観点でも企業にメリットをもたらす可能性がある。
「誘導策」に代わる対策を求める声
また専門家からは「太陽光発電の普及停滞を打破する方策として、設置義務化は有力な選択肢」という声も上がっている。環境建築学を専門とする東京大学の前真之准教授は、円安などの影響を受けてエネルギー価格の高騰が続けば、電気料金はさらに上がる可能性が高いため、太陽光発電の導入は住まい手にとっての経済的メリットが大きいと指摘。
その上で、余剰電力の買取や補助金などの「誘導策」での普及促進が限界を迎えつつあるなか、設置義務化は検討すべき選択肢と主張する。なお都の調査によると、都内の建物でのパネル設置率は約4%とされており、この数字を大きく引き上げていく義務化は現実的な選択肢だと言える。
批判が集まる論点は何か?
専門家がその必要性を指摘する太陽光パネルの設置義務化だが、冒頭で紹介したように、この制度案には批判も向けられている。
ここでは義務化に向かられた批判について、3つの論点を取り上げる。